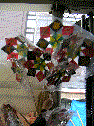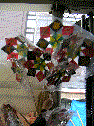加藤秀俊 日本あちこち耳学問
会津 福島県立博物館 佐々木長生さん
2005年1月13日
A:3月は雛流しと言って、いまの只見川にですね、紙で作った雛人形を女性の数、大人は大人、子どもは子どもの女性の数だけ作って、それを3月4日に只見川に流すんです。そういった行事がまだ残っておりまして、東日本では実際に雛流しをやるのはここだけだとおもいます。ちょっと上流に金山町というところがありまして、そこでは途絶えることなくずっとやっておりまして、今でもまだやっておりまして、地域差がかなりあります。集落によっては大人の人も作って流すとか、あとは子どもが中心になって大人の数もみんな集めて、そして集会所などに飾って、ヒナッコ(雛講)というものをやりながら子どもたちが一緒に舟を作って舟に入れて流すとか、サンダワラ(さん俵)に入れて流すとか、そういったやり方があるんです。
Q:ヒナッコというのは行事のことですか?
A:行事です。
Q:それはどういうことをするんですか?
A:甘酒を飲んだり、子どもたちが集まって、お雛様を飾って、そこで拝んでから川に流してやるという、その程度のことなんですが。その特色は舟を作ることですね。舟を作ったり、またはサンダワラといってこういう米俵の蓋ですが、そのサンダワラに入れて橋の上から流すとか、地域によって違いがあります。三島町の場合は、箱を作って子どもたちが全部、各家をまわってお雛様を箱におさめて、そして只見川の川に流してやると。金山町のその伝承は淡島の方に行くとかですね、淡島様は女性ですから。
Q:淡島は信仰と重なっているからね。
A:はい、そういったことを話されておりまして。金山町というところは、桃の節句ですから桃の花を飾って、その時に菱餅をあげるんです。ひし形に餅を小さく切って、そして和紙で帯のようなものを作って、これを背負わせて流してやるという、そういったやりかたがありまして。
Q:ここで言うお雛様というのは紙の人型ですか?
A:紙の人形ですね。こんな形で紙で作って。
Q:ああ、でも立派な紙人形ですね。
A:黒い紙で作って、背負わせているのはこれ、菱餅を背負わせているんです。
Q:このお人形を作るのも相当なことですね。
A:そうですね。大人の人が、そして今、子どもたちも真似しながらですね。慣れている人なら10分ぐらいでさっさと作っちゃって。私のところにも今、現物がありますが。
Q:ひとつの家から何体?
A:ひとり一体。女性。
Q:じゃあ所帯が5人だったら5体出すの?
A:女性だけ。
Q:女性だけ?
A:だからお嫁さんから子どもから、おばあちゃんもみんな含めて、だから女性が5人いれば5体。
Q:それはやはり、病気・災難よけということですか?
A:そうですね。
Q:病気の人はそれで流しちゃうという...?
A:病気でなくても、作るのは全部作りますが、やはりそういう信仰があります。災いをみんな代わりに流してくれるんだという。
Q:その河口部かどこかに淡島神社かなにかあるんですか?
A:淡島様はないですね。ただ、伝承で淡島の方に行くって言っているだけで。金山町の方で。
Q:でも流し雛をやって淡島様というのは一番オーソドックスですね。流し雛があるのは東日本でここだけ?
A:山形県の方でもあったと思うんですがね。それが今はやっていないかと思います。
Q:ねぷたなんかとは全く違いますね。
A:ねぷたもここはあるんですよ。ねぶた、ねむた流しと言っていて、実はここは「ねむた流し」なんですね。7月7日に子どもたちが、現在やっているところはですね、あの豆の葉で目をこすって眠り気を流してやるという方法なんですよ。これはねむた流しといって、山都町とか、喜多方市からちょっと西側の方にかなり残っておりまして。これは貞享2年ですから1685年の「風俗帳」というのが残っておりまして、この猪苗代とか各地の。「風俗帳」のなかに「ねむた流し」というのが出てくるんですよ。豆の葉で目をこすって眠り気を流してやるという、いわゆる青森のねぶた流しと同じような形ですね。それをやっているのは喜多方の奥から、奥というか新潟県の阿賀野川流域、それがなされている。江戸時代には各地域でそれをやっていたということが記録に残されています。
Q:「ねむた」というのは柳田先生の研究からいうと本来の意味に近いかんじですね。「ねぶた」よりも「ねむた」のほうが。
A:そうですね。「ねむた」ですね。だから会津はその三百年前の記録は「ねむた」です。「ねむ」の気、ねむた。それで邪気を流すんだということですね。
Q:このお雛様とか「ねむた」の方は旧でやっていらっしゃいますか、新でやっていらっしゃいますか?
A:今は新です。
Q:いつごろ変わりました?
A:「ねむた」はもう明治のころで、今やっているのは、ちょっとそこまで確認できませんが、だいたい戦後くらいかその頃だと思います。昭和三〇年ころ。だいたい戦争前まではほとんどここらへんの行事はお正月でも旧暦でやっていたということで。だからこの十日市なんかも旧暦でやると2月の10日から20日ごろですから、かなり大荒れのときだったでしょうね。今は新でやるからこう、わりと穏やかですが。
Q:十日市という以上は十日なんだけれども、それがほぼ小正月にあたるわけでしょ?
A:そうですね。
Q:この新・旧のことなんですが、韓国や中国の話を聞いていると、あちらは新にならないんですね。だいたい正月行事はアジアは旧でやっているけれど日本だけどうしてこんなになったんでしょうね。
A:戦後の終わりなのかねえ。
Q:明日拝見するのが十日市なので、あとでこれを拝見しますけれど、ここに来られる商いの方々というのはどこからおみえになるんですか?
A:現在はほとんど地元の方々が、地元の商店街とか農協の人がお出しになるんですが、今から10年くらい前まではテキ屋さんが多くトラックでこられて、今はテキ屋さんはほとんど姿を消して。やはり目につくのは新潟県の三条の刃物屋さんとか、あとは新潟関係は乾物屋さんなんかも多分そうだと思うんですがね。
Q:十日市全体を仕切る組合のようなものがあって、そこに...
A:そうです。申し込んでやるわけです。それは本部、商工会が中心となってやるようです。
Q:あと東北の各県からは特に...?
A:それはないですね。ほとんど地元の方々で。
Q:わたしは前に津軽の方の巡回市のことを少し勉強したことがあって。七日市があったり、三日市があったり、みんなトラックで移動しますでしょ?ここの十日市っていうのは、近くに七日市とか四日市とかありますか?
A:町内にあります。ここ会津若松市内のなかに三日町、七日町、八日町というのがあります。
Q:昔はその日に...
A:市がたっていたというわけですね。ちょっとここにも書いておきましたが、三日とか七日とか、そういうふうに決まっていまして、十日市は、会津若松全体ではなくて会津若松の商店の中心地は大町というところなんですね。大町は五の日と十の日だったんですね。それが十日が中心になって十日市という。これが初市、もともと若松町の一番の市になりますので、12月の29日、晦日のころから仮屋を作って、さきほどの風俗帳に書いてありますし、また詳しい資料もありますが、29日に仮屋を作って、そこに一斗の米を、五升は俵に詰めてあとの五升はいわゆる三方のようなものにお供えをしておく。それを年神様にあげるというようなことが書いてあるんですね。年神様にあげて、それを十日まで置いて、五升の俵にあげた方のものを群集のほうに投げて、これを奪い合う、引きあう、そして来年の米の作柄の占いをした、という行事なんですね。これは大町では明治4年までおこなっておりました。明治4年後、廃絶になりまして、これがずっと続いているのが会津高田町と会津坂下町なんです。坂下町は昭和32年ごろ、廃絶したのが、やはり明治維新以降、やはりやめちゃうんですね、それが坂下では昭和32年に復活して、高田はずっとそれをやっていたんです。それが今は巨大な3トンもある大俵になりましたが。もともとはこれくらいの俵なんですが。喜多方市の熊倉というところでは嘉永6年、だから1853年ごろになりますね。58,9年か。その嘉永6年の木札がついた俵が残っているんです。その俵を引くことによって来年の米の占いをするという行事に残っているんです。
Q:会津は大きな盆地ですけれども稲作はどうですか?
A:いいですね。私はこれを専門にやっているんですが、まわりが盆地なためにヤマセがあたらないんです。夏はまわりが山ですから、みんな伏流水となって全部この盆地にまわりから水が注いでいるんです。猪苗代から堰がありまして、そういったものも含んでくるというので、もともと稲作にはいい地帯です。古くは会津太湖といわれるくらい湿地帯だったといわれています。気候も内陸的な気候のために夏は温度がすごく上がるんです。稲の生育には、温度が一度にあがるものですから幸いなんです。だから水が豊富で天気がいいということで、お米もおいしいからおいしいお酒もできるという。
Q:会津藩は禄高はどれだけですか?
A:会津藩は23万石です。東北では仙台に次ぐ藩だったんですね。伊達政宗のいるころは百何万石ぐらいあったんですね、福島県の半分くらい。政宗は仙台に移封したときに。ここは上杉景勝がここに入ってくるんですね。そしてその上杉景勝が入ったあとに伊達政宗が入りますので。芦名、伊達、そのあとが上杉ですね。そして今度は保科が入ってくるわけですね。そして松平藩になって。
Q:上杉は越後からですよね?
A:越後からです。
Q:そうするとここは交通としては新潟に一番近いんですか?さきほどの三条の刃物の話もありましたが。
A:ああ、そうですね。若松はやはり新潟には近いですね。今の交通の便からいっても福島に行くよりは新潟に行く方が近いぐらいですね。
Q:只見を越えればいいんですね。
A:いや、只見を越えないでこちらからまっすぐ西会津のほうから。只見を越えちゃうと長岡方面になるんですね。新潟市だとこちらの西会津の方から。
Q:長野の人が意外と新潟に近いんですね。
A:そうですね、今の十日町、あのへんからずっと。あとはここがなぜ会津の国になったかという古事記の中にも伝承が出てくるんです。オオヒコノミコトとタケヌワケノミコト、いわゆる四尊将軍の伝承なんですが。ここでオオヒコノミコトとタケヌワケノミコトと、越後の方から、要するに越の国から来たのと、あとこっちの常陸のほうから入った神様同士ですね。ここで、神様が津のところで会った。津というのは今の猪苗代湖の、または川がいっぱい集まりますから、この会津坂下町あたりで、そこで神様が会ったという古事記にあるこの伝承。だから津で会った、ということで相津という地名なんですね。その相津という地名がついてくるわけなんですが、それは単に神様が会ったというよりもむしろ文化が出会ったと。だから越後の文化と、つまり北陸の文化ですね。関東の文化は今の茨城県の方にそそぐ久慈川の文化ですね。久慈川の文化と阿賀野川の文化が出合う、ということで。こちらには古志王神社という、コは「古い」、シは「志」、そして「王」と書く、あとは「コシ」は人間の「腰」とか、あとは「王子」の「王」と書く、これは越の国の、ということからそういう信仰が言われているとおもうんですが、そういう神社が点々とありまして、喜多方でもたいへん著名な古志王神社などがあります。これがいわゆる会津の、ここの前館長の高橋富雄さんがよくそういうことをおっしゃっておりましたが、わたしもそれはそうかなあと思います。また、関東から入ってくるのは久慈川の、棚倉町というのがありまして、ここには都々古別神社というのが。これは展示の方にもありますが。そこは奥州一宮だったんですね。かつてはそこが一宮なんです。ですからこちらから入って来たんじゃないかなということですね。
Q:そうすると、廃藩置県で福島県が置かれても、むしろ福島っていうのは...
A:板倉藩で、二万石ですからね。二万から三万石ですから。ここは、明治の、終戦ごろの時は若松県と磐前県という、福島県という県ができるんですね。これは展示の方で紹介してありますが。その若松県がつくられて、今の会津のほうは若松県だったんです。ところが、やはり明治維新であれだけの変化がしてますから、それでこんどは福島県は明治9年に合併されます。そのときに一番、今でこそ道路がよくなって、ここから1時間半で福島まで出られますが、そのころは、ぐるっと回って東北本線沿いに行きますと...
Q:まあ、要するに会津は明治政府にあれだけ意地悪されて... 津軽も意地悪されて。
A:そう、津軽。あと天童、庄内とかですね。そういったいみで、その当時、最初はですね、今の新潟県の東蒲原郡。あそこまで会津藩だったんですね。だから明治9年に合併されるまでは、いまの東蒲原郡は若松県だったんです。今の福島県に入っていたんです。それが、あと、あそこは新潟の人たちの先祖は昔は会津だとかね、言われているんです。
Q:じゃあ新潟のこう、出たところの人たちは非常に会津に...
A:そうそう、親近感があるんです。だから、たとえばここ若松に会津高校ってあるんですが、これは旧制の会津中学ですので新潟の方の人たちはここでわざわざ下宿しながら会津中学に入ったんですね。今、亡くなった赤城源三郎先生などはその一人です。やっぱり、そういったことでわざわざ来て入った。そういう方々はけっこう多いですね。
Q:それとつながっている話かどうかわからないけれども、この間からちょっと疑問に思っていたのは、福島県立博物館が福島でも郡山でもなく、会津に来た、このいきさつをちょっと伺いたいんですが。
A:まず、やはり福島県の歴史ということになると会津がやっぱり、たとえば若松のお城にしろ、たとえば仙台だったら仙台そのものですよね。やっぱり福島県には各小藩がいっぱい、小さな藩が、五万石、六万石とか、そういう藩がいっぱいある。白河、二本松、相馬、磐城とかですね。ところが、これは仙台に次ぐ大都市ですので、当時としては。ということと、多くの方々が磐梯山とか、裏磐梯とか、そういった歴史、文化、自然を含めてですね、多くあるということでここに福島県の、県民だけでなくて全国の方に見てもらおうと、福島を、それでこの会津ということに。このすぐそばがお城ですので。ここは三の丸の跡なんですね。旧、かつての馬場跡になっているわけですね。ですからそういった意味でもここの敷地は会津若松市から県の方に提供いただいて作ったわけです。
Q:福島と郡山といつも緊張関係があって....
A:あとですね、その当時、福島県は文化100年というような構想がありまして、その当時の知事が殿様の系統なんです。松平勇雄といって、国務大臣の松平恒夫と従兄弟関係でして、その松平勇雄というのがもともと、ここ会津候の親族なものですから、それで自分が知事の時に、図書館と美術館を福島に作って、博物館をこっちのほうに作る。そして磐城には海洋博物館を作ろうという構想がありまして、そして磐城に平成10年に海洋博物館を作ったんです。アクアマリンふくしまという、水族館と科学館と、そっちのほうに2年ばかり準備で仕事をしてたんですが。
Q:文化施設は県内に分散していたほうがよろしいですからね。
A:それで、その文化施設と、教育施設を分散するというような方針をとって、それでこういうことで。
Q:来られたのは...
A:昭和61年です。だからもう20年ちかいですね。ここはやはりお城の中ということで、いわゆる箱物を鉄筋コンクリートビルにしないで、この平屋建てにして、倉造りを模しているわけです。そして景観をこわさない歴史的環境。だからこの隣にある学校も、ビルにしないでやはり倉造りにしたり、その前にあるガソリンスタンドまで平屋建てで作るっていう、そういう規制をされているわけですね。
Q:それはしかも県内で見たときに近世、あるいはそれ以前にさかのぼる文書もおそらく会津が一番でしょ?
A:多いです。あと民俗もそうですね。私は農業のほうを専門に、とくに民具について、貞享元年に佐瀬与次右衛門という人が「会津農書」という農業技術書を書いておりまして、わたしはそちらのほうをずっとやっておりまして。この「会津農書」は「農業全書」より13年も早いですね。そして、著者がはっきりしている、著作年代がはっきりしているという。その前にもいろんな農書があるんですけれど、みんな著者や著述年代が明確じゃないんですね。そういったことで「会津農書」は、ひとりの人間が何冊も農書を書くんですね。最初は農業技術、上・中・下。稲作、畑作、とはいって、そのあとにまたわかりにくいっていうこともありますが、1697つの歌でつづってある「会津歌農書」っていうのを書いて、「歌農書」のあとで19年間にわたる天気のデータをとっているんですね。それと作物の出来具合とかですね。そういったものまで書いている。ひとりの人が何冊もの農書を書いている。幕内っていう、「会津幕之内誌」っていうんですが、そこの庄屋さまだったわけです。
Q:何ていう方ですか?
A:佐瀬与次右衛門(させ・よじえもん)というんです。「さ」は「佐々木」の「さ」と、あとは「瀬戸内海」の「瀬」、あと「よ」は「与える」、「じ」は「次ぐ」っていう字ですね。そこに「右」っていう字がはいって「右衛門」なんですね。こうやって書いて「よじえもん」と読ませるんですね。これが農書として、この書いてあることが今でも残って、農業にも通じているんですが。
Q:さきほどから稲作には大変適しているというおはなし伺いましたけれども、弥生の遺跡っていうのはありますか?
A:ここは弥生はわりあい少ないです。縄文はけっこういっぱいあるんですが。
Q:このごろの学説だと縄文後期で米を作っていたと。
A:そうですね。板付(福岡県)とか菜畑(佐賀県)とかあの辺で。ここは縄文の後期の遺跡がありまして、さっきの雛流しをやっている三島町の。雛流しをやっているところで荒屋敷遺跡というのがあって、これは三内丸山をミニチュア化したようなところで、土偶は出てくる、布は出てくる、籠は出てくる、弓が出てくる、漆が出てくる、っていう本当にすばらしい、漆塗りの土器まで出てきたりですね。ほんとうにすごいものがあるんです。食べものじゃ、トチ、ドングリ、クルミ、そういったものも出てきている。
Q:でも新潟も米どころなんだから、もみが出てきても不思議ではないですがやっぱりちょっと寒いですかね。
A:そうですね、やっぱり縄文の。津軽の稲作っていう村の垂柳遺跡っていうのは弥生のころの水田の跡が発見されています。だから会津にも、ただまだそういう遺跡に出くわしていないっていうことで。弥生時代の遺跡も山間部で、金山町に宮崎遺跡っていうのがありまして、ここにはそういった、稲作まではないですが、山間部でV字谷の只見川の流域なものですから、そういった農耕はあまり出てこないですが弥生の土器は出ています。そして若干、その只見から三島町からそのとなりに柳津町っていうところがあるんですがそのへんは新潟県の長岡近辺のですね、火炎土器がここまでのびてきています。そういった意味で、私たちの民俗の藁人形を作るとかいう行事を見ても、やはり信州から新潟、その辺とつながっていますいね。道祖神とか。
Q:東北といいますと、私は岩手県が一番いままでいろいろ勉強したんですけれども、岩手に行きますと、米っていうのは配給制になるまで食ったことがない、と。山の中に行くと、よくお年寄りのかたがおられましたけれども、会津の方は要するにちゃんと米を食べていたんですね。
A:米は食べていますね。ただ、少ないところは、たとえば桧枝岐村っていうところには田んぼはありません。海抜が950mぐらいありますから。ここはなかなか米が食べられなくて、やはりヒエ、アワが中心ですね。だからヒエも食べたけれど、ヒエは精白するのがむずかしいっていうのでアワですね。隣の滝岩村ではカブですね、赤カブ。カブをごはんに入れて、カブ飯とか。あまったるこくてね。これも焼畑で。ヒエも焼畑で。
Q:焼畑はいつごろまでやっていましたか?
A:昭和35,6年ころまで。ただ、私が確認したのでいちばん遅いので昭和35,6年。ソバを作る人たちは焼いてやったという、私も今月の末あたりで、ここの館長が、今、赤坂憲雄さんっていう方が館長になって来ているんですが、今回は佐々木高明先生が去年、東北芸術工科大学に来て、今回の特集が焼畑、稲作文化再考学とかいう。
Q:佐々木高明は私の昔からの親友です。
A:私もずっとお世話になって、去年の7月も山形でいっしょでした。
Q:ああ、そうですか。私も佐々木君に連れられて白山の奥まで行って。
A:ああ、小峰村とか。
Q:そう、そう。
A:ずっとお世話になって、民博の会議の委員なんかでも先生から推薦されて10年くらいやりました。山形でその高明先生が講演をやって、あと佐藤雄一郎さん、あのDNAの遺伝子の、それの講演とかいろいろ集めたものを、各地の焼畑についてわたしも今年の1月の末に出るものだっていうので昨日、原稿を送ったばっかりなんです。
Q:焼畑の話は聞くんで、山梨県の早川町とか、足は運んでいるんですけれどもとっくになくなっちゃっていますね。
A:ここはやはり、いま言ったような金山町とか、あと只見町、そのへんにかけて焼畑はカノと呼んでいますがね。そして、初年がやっぱりソバなんですが、土地のちょっといいところはカブを作るんです。赤カブを。そして最後はアズキを作って終わり、という。カブ、あとはアワですね。最初はソバ、カブ、アワですね。そして最後に大豆。あとカブと大根を植えるところもあります。焼畑では、ソバは夏ガノと呼んでいますので、夏物はソバなんですね。そしてヒエは春なんですね。ヒエもとるんです、これは江戸時代にかなり、そして今、ヒエのことを書いているんですが、焼畑でやはりヒエもだいぶとっておりまして。そしておもしろいのは、ヒエを焼畑でやっていた宮本常一先生が、日本文化の形成の中で田稗の中であつかっているんですね、田んぼの。それが下北半島とあと佐渡のほうの、その田稗の栽培方法が会津農書にはっきり出てくるんです。「稗田」ということで、田んぼの田稗と。これは東北では田稗のものを扱っているのは現在、これとあとは岩手県と青森県の境にある九戸郡の軽米町。あそこではかなり田稗を作っていたようですね。軽米町のところでは文化何年だったか、ちょっと今、年代を忘れましたけれど「軽邑耕作鈔」っていう農書があるんです。ここに田稗の耕作方法が詳しく書いてありまして、あれは田稗のものでは最高のものですね。それはずっとあとになりますが、ただ古い年代のものでは「会津農書」が一番古いですね。ヒエの作業の時に切って、それから植えるっていう方法。そんなことを宮本先生の、たとえばヒエが三内丸山で最近出ていますので、ヒエの栽培がああいう焼畑栽培があったからこそ、たとえば垂柳遺跡のようにたとえばそこで田植えがあったとすれば、稲作が入っている、というのは、宮本先生はどうもそういうようなことをお書きになっていたと思うんですが、わたしはああ、これだと思いながらこの田稗の問題を今回扱ってみたんですが。やっぱりシコクビエという、方々で作っている、あのシコクビエもみんな田植えのように植えるんですよね。だから田稗も一回、ヒエがないところに作って、そして一回、田んぼに植えるって書いてあるんです。だからそういったことから考えれば、ヒエが、まして坂本寧男さんっていうんですかね、大阪の生態民族学っていうんですか、雑穀の問題をお書きになっている先生によると、やっぱりヒエっていうのはインドビエから改良した、インドビエとは違ってあれは日本から満州までいくと。ところがヒエっていうのは漢民族は食べないそうですね。
Q:アワですね。
A:はい、アワで。そしてこれも宮本先生の引用なんですが、漢民族は食べないけれどツングス族や満州族は食べるそうですね。どうも、そうすると宮本先生の壮大な構想っていうのは、向こうから稲を持ってきた民族が満州族であれば、たとえば漢字っていうのが漢民族が持ってきたものだとすれば、だからヒエっていうのは漢民族は食べないから、ヒエっていうのはコメ扁に「卑しい」っていう字を書いたのかなあ、なんてずっと詮索していたんですが。会津では「ヒエ」っていう字は禾扁に参考の「参」という字を書くんです。それでその下に「子ども」の「子」っていう字を書いてそれでヒエって読むんです。
Q:のぎへんに何ですか?
A:のぎへんに「参考」の「参」です。これでヒエと読みます。決してヒエは、会津農書の中などではヒエは干魃にも強いし、冷害にも強い、寒さにも強い、アワよりもいいんだと、アワと旧耕作、アワとヒエ。アワはたしかに多く災害にあう。ヒエは寒くても暑くても、なんでもとれるんだと、だからヒエを作りなさいと会津農書は教えていますね。
Q:このシコクビエは佐々木君に連れて行ってもらって白山のずっと上のほうまで行きましてね、そこでシコクビエの練ったのをごちそうになりましたけれども。で、あのシコクビエということばがいったいどこから来ているのでしょうかね。なかなかよくわからないけれど。
A:そしてヒエの問題でも、奈良県の大東村とか、いろんな、あとはゾロビエとか、あとは新潟県と長野県の境の秋山も、あそこではオロカビエとかって言っていますね。オロカとかゾロビエとか、あとはイヌアワっていうところもあったそうで、イヌっていうのは偽物だっていうような意味があるらしいです。そしてゾロビエっていうのは、ゾロゾロ出てくるっていう。あとヒエっていうのは原種があれなもんで、すぐ種から種をちゃんととっておいて、種をとって、実ったところからすぐに種をとって植えれば品種は衰えないんですが、それが落ちてしまって、出たものから種をとっても原種に帰ってしまう、という、そういったことが会津農書の中に書いてありまして。すぐ帰ってしまう、と。奈良県の大東村や秋山のほうではゾロビエとかオロカビエだと言うのは、どうも種が落ちて、そこから出たのがゾロゾロと出てきて、だからゾロビエだっていうんです。だからそういう野生化したものを栽培したから、すぐ戻っちゃうらしいですね。会津農書でおもしろいのは、ヒエはウマジリヒエとか言うんですね。馬のお尻。ウマジリビエとかっていう言い方をしている。そしてアワはイヌジリアワ。動物がこう、出てきているんですね。たしかに会津の人なんかでは、アワはイノコログサから出てきますので犬だという。そしてヒエはマジリビエって言う。そしてなぜヒエをマジリビエっていう言葉になるかということを会津の人の場合は出てくるんですが、これはもともと田んぼの中に出たヒエを、雑草として出たヒエを栽培する。それを畑のほうに飛んで混じっていっってワーッと増えたのは、これでマジリビエだから。これは雑草になってしまったものです。それに対して田稗はちゃんとちゃんと栽培していれば農作物です。
Q:そうやってお話をうかがってて、ずっと農業のほうがご専門だと伺いましたが、やはり栽培植物の中ではやはり会津では米作中心ですか?
A:米作中心ですね。ここは、「会津農書」は米が中心でありながら、ただ畑作物の記載が詳しいんですよ。それは佐瀬与次右衛門は「会津農書」を書いた時にですね、小農民っていうんですか、自立したばかりの農民、そうするとそういう人たちが安定した農業をおこなって安定した年貢を出せるようにというために庄屋様は農書を書くんですがね。供出する米をほとんど農民は米はほとんど全部出してしまうと。そうすると、それを補助策として今度は畑作物をやるから畑作物を細かに書いているんです。その畑作物も「糧菜」といって、野山の水とかドングリとか、そういったものもとって食べなさい、と。だから「会津農書」の記載の中には「糧菜」、「糧菜蓄え」と、野山のそういうものをとって食べなさい、という記述もあります。
Q:それは救荒植物ですね。
A:救荒植物でないんだけれども、それぐらいの心構えで食べなさいという。大変おもしろい記録ですね。
Q:郷土の年中行事のほうに戻りまして、ネブタのほうから流し雛にいたる一連の行事ですよね、これがどうも、今までほうぼう東北各県で拝見していたのとこことはちょっと様子が違うようなかんじですが、これはどんな伝播経路があったんでしょうか。
A:伝播経路はちょっと、わからないですね。やはりわたしは....
Q:だいたい流し雛っていうのは上方のものですよね。
A:私はやっぱり只見川っていう、川の文化だと思うんです。もうひとつは、ここの塩の道は、阿賀野川流域ですね、これは寛文何年かですか、ここの川を、寛文12、3年だったと思いますが、この只見川も新潟からここまでの水路がやはり改革されてくるわけですね。そうすると西廻りの塩が入ってくるわけですね。それまでは太平洋側のほうから塩が入ってきたということなんですね。そうすると、あと鉄なんかもさっき言ったように、古い時代は棚倉からこっちに入ってきたという。そういう記録もあるんですね。ところがそれ以前に、やはりここは文化的な面とかなにかいうと会津の場合は新潟の文化が本当に強いんです。だからその、たとえばさっきの、藁人形を作って、こういったふうに焼くのはほとんど信州から新潟にかけて藁人形っていうのは多いんですね。これなんかはずっと入ってきて会津がいちばん多くなって、まあ、会津でやっているところは一ケ所ぐらいしかないんですが。こういったものとか、あと双体道祖神なんかの分布を見ても、どうも会津のことを考えれば西廻りのほうが多いですね、やっぱり中部の。中部的な。
Q:双体道祖神はかなりあるんですか?
A:その三島町のほうにだいたい12,3体あります。
Q:信州に行けば...
A:いっぱいありますが。それはですね、どうも安永のころの、決して古いとはいえませんが安永のころの年代のものが多いです。安永2年、3年。1770年、天明が1770ですから...まあ、安永のころですね。安永の2,3年のものが多いですね。もともとは双体道祖神は元禄の年号が入っている双体道祖神があるんですがね。これは田島町っていうところに。その田島町の滝ノ原という、すぐ隣がもう栃木県なんですがね。これには元禄4年だか5年の年号があって、そして安永の2年か3年に作り直しされた。だから元禄のころのは単なる石かなにかだったかもしれないですね。安永2年、3年のころに作り変えたというのが双体道祖神、こう手を握って。それから隣の昭和村とかあとは金山町だとか、そういったところに行くと安永2年、3年の同じような顔をした双体道祖神がありますね。
Q:おもしろいっていうか、複雑ですね、会津文化っていうのは。つまり、越の国とつながっているとすると北前船文化がどこかに入っているでしょうしね。
A:北前はどんどん入っています。また会津藩では北前は新潟から入ってきて、そこから古手物、着物ですね。古着。そういったものが会津藩の中には入っています。古着とかそういったものは、新潟から入ってきています。それから、私もちょっと興味を持って舟のことをちょっと調べているんですが、河村瑞軒のころですね、やっぱり水路ができなかった。難所なんです、急流で。そういうところを舟は荷物をおろして、舟だけをひっぱるんですね。それの絵が描いてあったのがありまして、それを見ると、その舟が新潟とかの方の信濃川の方の舟と同じ舟なんですね。それがわたしは今、舟のことを調べていて、だいたい5,6点、だいたい同じような絵が出ているんですが。ここに出ていますね。だからそういったことだと、信濃川のほうのやつと何かよく似ておりますね。そしてそこに描かれている舟の形、そこに描かれている図なんかもほかとよく似ておりまして、もうひとつ、天当船という舟がありまして、これは川舟なんですが、やっぱり西日本からずっとついながっていて、今、会津坂下町に天当供養だか天当なんとかというものがあって、その天当が立っているところが阿賀野川、只見川の流域なものですから、これも当時の舟から物を運んだときの何かの名残かなあと。
Q:川舟だから平底ですか?
A:平底ですね。
Q:最上川はどうですか?
A:最上川とはここは関係ないです。最上川はもう米沢から主流になりますから、ここはみんな只見川、阿賀川の。
Q:いえ、舟の。
A:舟の形は最上川のほうはわたしもまだ調べていないので。多分おなじ形とは思うんですがね。
Q:去年の夏、最上川流域をちょっと見たんですがね、舟のことはちょっと気がつかなかったので。もうめったにできなくなりましたしね、ダムのおかげで。
A:今、うちのほうでもですね、船大工さんに作ってもらった船を縮小して、そのままの形に作ってもらった船があるんですが。「ヒラタブネ」っていうんですね。
Q:とても勉強になりました。とりわけ、私たちの世代も含めて、私よりも若い人たちはさらにそうなんだけれど、福島県というので、もうここにあるんだと、福島県を頭の中に置いちゃっていますから、県と文化はまったく違うでしょ?
A:違います。私はここ会津に住んでいま32年目なんですが、もともと生まれは相馬っていう浜通り、太平洋側なんですよ。私の家はもう、今の季節だと寝てると波の音がザブ、ザブ、と聞こえるようなところで生まれたものですから。こちらに来てもう20年になりまして、私は野口英世記念館のすぐ近くに会津民俗館という民俗資料館がありまして、私はそこに12年勤務しておりまして。で、会津地方をかけめぐりながら民具を蒐集して、今日、展示してあります仕事着、刺し子、そういったものを整理したりという、本当にもう、机の上の勉強でなくておじいちゃん、おばあちゃんから習った勉強をずいぶんやってきて、そしてこの博物館を創るときに公募があって、入ったということなんです。その後にたまたま前の文化庁におられた木下先生に、唐箕の研究をしたんですね。会津には半唐箕という変わった唐箕トウミがありまして、その本唐箕っていうのは両脇についているんですね。半唐箕というのは両脇ではなくて真下に出る古い形の唐箕があるんです。それを小坂広志さんという方が、米沢に会津の北田久内の天保8年の唐箕があるっていうのですぐに調べて、それを木下先生にお渡しして。こんどは木下先生は私のところに、今度は佐々木さんのところにありますかっていうから、わたしは正直言って知らなかったんです。そしてすぐ調べたところ自分の資料館の屋根裏にあがっていたのを見つけて、木下先生にはこうだ、と。その時に私は半唐箕の報告を書いたんです。その時に「会津農書」の中に、やっぱり農業だからその中に唐箕が出てくることを私は書いたんですね。そうしたらそれが日本で一番古い唐箕使用の記録になってしまったんですよ。それを木下先生が、昭和19年に伊藤書店から小野武夫さんが作った「会津農書」という本がありまして、そのとき小野武夫さんは急いで作って福島大学にいた庄司吉之助先生っていう人がいらっしゃいまして。庄司先生がやったのを提供したのを小野先生が編集して、本にされたんですね。ただその、脱落している部分があって、それをこんどは地元の、「会津農書」が生まれたところで、長谷川吉次さんという人がおられて。もう一回「会津農書」を作られたんですね。その「会津農書」を私は引用したから、そしてその時に伊藤書店の本なんか持っていなかった。その時は半唐箕の報告を書いた時に木下先生がそれを見て、たまげた。木下先生がそれを伊藤書店の本で見た、って。なんぼ見てもその唐箕のことをさがせなくて。どこにのってんだって言ったら、何ページの何々にのってますって。それで今度は伊藤書店の本でまたさがして、次の日に電話をくださって、こう、それで、私が「会津農書」の仕事をしたきっかけになるわけです。昭和54年だったですが。それ以来、木下先生にはもう、「会津農書」の研究は一生涯のテーマですよ、なんて言われたら一生涯のテーマになって。
Q:一県一文化っていうのが、かろうじてあるとすれば、南部は多少そうかもしれない、岩手やね。
A:それに似て、会津だけで県内独立文化なんですね。
Q:そうですね。
A:本来だと、明治のあれだと、ここは福島県ではなくて完全に若松県でよかったんですよ。
Q:そうだと思います。あんまりいりもしないところを一緒にしたり、へんなことをしましたからね。
A:これはどうしても、福島県にしてしまって、県庁をみんな向こうに持っていって、ここにはまだ立てこもらんといけません。
Q:かわいそうなのは、弘前もかわいそうですね。
A:そうですね。青森に持っていかれて。本来だったら向こうですからね。
Q:弘前は本当にかわいそうでしょうがないんですけれど。
A:それで私なんかはよそから来た者で、会津に来て住んで、今だから、会津はやっぱりそういったことで、漢字の「国」でなくてカタカナの「クニ」っていう字を使うと。やっぱり会津はひとつの国ですね。
Q:いま来るとき、タクシーの運転手さんに中通りと会津とどこが境なの、って聞いたら、熱海って言ってました?
A:そうですね。熱海、今でこそ行政的には郡山市って言っていますが。猪苗代湖、本来は磐梯熱海からずっと西にのぼってきて磐梯山が見えたとき、あそこからもう会津の里なんですよ。猪苗代湖の真ん中があると、猪苗代湖は今の行政でいうと猪苗代町と、会津若松市と、あと郡山市と、この3つに分かれているんですよ。だから郡山市の猪苗代湖は海抜514メートルあるんですよ。そうすると郡山市といっても、旧安積郡といってもですね、文化圏は会津なんですよ。福島県は真ん中に猪苗代湖があり、福島県のヘソと言われていて、だからこの、奥羽山脈のこっちですね。磐梯熱海からこっち側は全部もう、風土的に会津なんです。そういうことを言うと福島県の半分が会津なんですね。この会津には、わたしは会津の民俗をひとことで言えといわれた時にはよく、この会津の三泣きっていうことばがあるんですよ。福島県はこれだけ広いのに、たとえば学校の先生になると最初の年はこの会津の方に転勤させられるんです。初任者は。そうすると会津っていうのは、やはり一国主義、国主義ですから、よそから来たものに対してはよそ者っていうことで、差別ですね。そこで一回泣かされるんです。ところがつきあって一年ぐらい経つと、先生、大根とれたから大根食わせ、なんて言って大根持ってくるんですよ。そうすると、あ、最初はあんなに冷たくされたのに本当はいい人だったんだな、なんて2回泣かされる。だいたい3,4年たっていくと、こんどは地元の浜通りとか中通りなんかに転勤にされて。またこんど、ここの人たちと別れるっていうことで泣かされて。これが三泣き。あとは会津の盆地とか雪とか、そういったことがそんな民族性をつくっているのかなあと。まあ、それが野口英世の忍耐力とか、あとは会津の人は頑固だからなっていうコマーシャルがあったんですがまさにそんなあれがあるのかなあ、と思って。
Q:いろいろとありがとうございました。
加藤秀俊著作データベース
文書管理番号: 3038